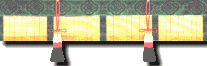 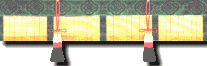 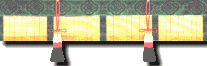
 製造編 製造編 
*「蘇庵」ブログに掲載中の物を編集しました。

 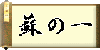 
 延喜式、不親切なレシピ... 延喜式、不親切なレシピ...
当HP、ブログではお馴染みになりました、延喜式に記されている唯一の「作蘇の法 」
「乳大一斗ヲ煎り、蘇大一升ヲ得ル」
これがまた不親切なレシピであった為に困惑された方も多いかと思います。私なりに
ひも解いてみましたのでこれから作ってみようとお考えの御仁は参考にしてみて下さ
い。
まず、乳とは牛から搾った生の乳=生乳
大升一斗とは古代尺貫法によると大升一升は
現在の四合(720ミリリットル)換算なので=7.2リットル
(当初私は素直に18リットル(一斗)の生乳を二十時間以上煮つづけて睡魔との戦いの末
結局は焦がしてしまった。という失態を犯している、今なら7,2リットルであれば9時間
程で蘇庵の蘇は完成する。)
煎るとは、当時煮ることを煎ると云ったそうです
蘇を作る人の事を「煎り人」と呼んでいました。=煮る
蘇とは=生乳を煮つめた物
大升一升とは=720ml
ということで「7.2リットルの生乳を煮つめると、720mlの蘇ができる」
「生乳を十分の一に濃縮しなさいよ」と簡単に解釈して作ってみたが、そう単純な事で
はなかった。火加減にしてもすべてが手探りであり、何度も焦がしてはため息を付き鍋
をひとつダメにしてようやく気づいた。
「牛乳の全固形分は約13%である」どんなにすぐれた料理人でも十分の一に濃縮するの
は無理な話であったのだ...。

先頭へ

 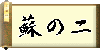 
 十分の一の謎... 十分の一の謎...
古代牛の全乳固形分は10%以下であったのだろうか? 現代のホルスタイン種の全乳固
形分は約13%前後である。
昭和60年頃は12%前後
昭和40年頃は11%前後
昭和20年頃は10%代 と低かったようだ。
であれば1200年前の古代牛の全乳固形分が10%以下であったとしても不思議ではない。
粗末なエサに適当な飼育法であればそんな物だろうと高を括っていた...。
ところが某大学の研究レポートには、現代黒毛和牛、短角牛の泌乳期の全乳固形分は
14%以上になるという結果がグラフに記されていた。私が予想していた数値より遥かに
高くジャージー種並であったのだ。そして古代日本史料のひとつ「正倉院文書」正税帳
には、搾乳牛に与える飼料給与量などが事細かに記載されていた、これは飲用としてで
はなく蘇を作る為の搾乳、飼育法なのである。これで1200年前(古代牛)の乳成分は低か
ったのだろうと安易に断定できなくなってしまった。
十分の一の濃縮には諸説ある。 例えば重量比ではなく容量比ではなかろうかと唱える
考古学者もいる。
要するに古代調理器具は稚拙なものであった為にコゲなどにより蘇の収量が少なかった
のではなかろうかというものだ。
実際に蘇を作った方々は一様にうなずきたいところだろう。何故なら乳はとても焦げや
すく、八分の一の濃縮さえも儘ならず四苦八苦して出来た物は鍋と同化したミルク臭の
する残骸であったと推察されるからだ。
ここで、今更ではあるが蘇を語る前にまずは紹介しなければならなかった
のが奈良県「みるく工房飛鳥」さんの「飛鳥の蘇」である。現代に「蘇」を蘇らせ全国
に広め、その味を知らしめたのはパイオニア的存在の「みるく工房飛鳥」さんに他なら
ない、褐色の塊の中に古代を彷彿させる魅力がある。まだ蘇を食した事の無い方には、
まずは「飛鳥の蘇」を是非召し上がっていただきたい。飴を練る機械での製造という
が、餡練機のようなものなのか定かではないが、ガス釜での火加減はやはり相当に難し
いと思う。
ところで個人的に蘇を作り、楽しんでおられる方々もこちらの「飛鳥の蘇」のおかげ
で十分の一の呪縛から解き放たれたのでは無いだろうか...。

先頭へ

 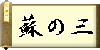 
 十分の一の謎 (補足) 十分の一の謎 (補足)
仮に古代牛の全乳固形分が8%だったとしよう、十分の一に 濃縮すると蘇の乳固形分
は80%となり残り20%が水分となる。
バターに含まれる水分は約17%、フ゜ロセスチーズで約45%であるので硬い固形物であ
ることは想像が付くだろう。
ちなみに蘇庵の蘇の水分量は通常約30%である。(もちろん冷蔵温度範囲での話である
し、乳成分も違うので比較するには無理があるが...。)
食べかけのチーズをいい加減にラップをして冷蔵庫に保存していたらカビてしまった
という経験はないだろうか。チーズとラップの間に水分が溜まり細菌が繁殖した訳であ
る。逆にラップもせずに冷蔵庫に放置し、忘れた頃に出してみたらカチカチに乾いてい
たなんて事もあったと思う。
冷蔵庫でなくても、条件さえ整えば、細菌が繁殖する前にほとんどの水分を無くすこ
とは可能であると考えられる。実際に冬場、蘇庵の蘇(水分量約30%)を小壷に入れ和紙
で蓋をし室内に放置しておいたところカビる事もなく一ヶ月でカラカラの状態となっ
た。以外や十分の一の正体はこれかも知れない。遠い諸国から都へ何日もかけて運ばれ
る途中で八分の一程度に濃縮されいた蘇が宮中に辿り着く頃には十分の一に乾燥してい
た。壷に入れ貢納したのは濃縮率が一見してそれと判る為であったとすれば...。
なんだかもうこじ付けになってきたので、この謎解きは学者先生にお任せする事にし
よう。何故なら私が作りたかった蘇は他にあるからだ。
「延喜式」、木簡などに記された貢蘇諸国における「精蘇」と「生蘇」の違いを
新たに認識し、さらに悩まされる事となったのです...。
(現代では、スタンダダイザー(三元分離機)などの機械処理で乳成分が思いのままに
調整出来るらしい、機会があれば全乳固形分8%の生乳に調整してもらい、マイ鍋で十分
の一に濃縮した蘇を作ってみたいと思うのだが、大手乳業メーカーにでも就職しないか
ぎり無理だろうな。)

先頭へ

 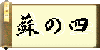 
 「精蘇」と「生蘇」 「精蘇」と「生蘇」
牛乳はとても栄養価の高い食品であるが細菌にとっても格好の 培地でもある。
水分量が多いほど痛みやすい訳であるから出来るだけ濃縮率を上げ水分の少ない蘇に仕
上げれば保存が利く。
「延喜式」による十分の一の濃縮は、質の安定と保存が目的であり、遠い諸国からの運
搬にも都合が良かったのであろう。このほとんどカラカラに乾いた状態の蘇を「精蘇」
とよんでいたようである。直接食べるというよりは、主に薬餌として使用していたので
はないだろうか。
貢蘇制度が確立した当初は「生蘇」なる物も貢納されていた。平城宮跡から出土した
木簡の中に「近江国生蘇三合」という書付がある。恐らく水分量が多めの柔らかいタイ
プの蘇であったと推察される。運搬途中でカビが発生したり腐敗する事も度々遭ったに
違いない次第に近隣諸国からのみの物となり、後に「延喜式」の発動により、十分の一
の濃縮に統一され「精蘇」のみとなるのである。
では「生蘇」の製造は中止されてしまったのだろうか。
ここで長屋王邸跡から出土したふたつの木簡に書かれた内容を紹介したい、非常に興
味深いものである。
A「牛乳持参人米七合五勺 受丙万呂九月十五日」
B「牛乳煎人一口米七合五夕 受稲万呂」
Aの木簡には「牛乳を納品した丙万呂は米を七合五勺褒美に受け取った」。
Bの木簡は「蘇を作った稲万呂は米を七合五勺褒美に受け取った」という書付である。
おそらく邸内にある乳牛院(乳製品加工所)に、近隣の乳戸(酪農家丙万呂)より質の良い
新鮮な乳を運ばせ、腕の良い煎人(蘇を作る人稲万呂)を雇い入れ蘇を作らせたのでは無
いだろうか。そして朝廷の御膳に上げられ、高官、貴族たちの華やかな宴に添えられ
た。そう、この特別な蘇こそが製造中止かと思われた「生蘇」であると考えられる。
もうお気づきであろう、「蘇庵の蘇」はこの特別に作らせていた蘇、「生蘇」を再現
した物なのである。

先頭へ

 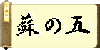 
 蘇庵の蘇 蘇庵の蘇
蘇を作り始めた当初は何とか十分の一の濃縮に近づくよう工夫を凝らすが、八分の一
程度がやっとであった。市販のローファット乳、成分調整乳を使ってみたり、わざわざ
水を加え成分を薄めてから濃縮した事さえもあったが、結果は鍋と同化したコゲだかミ
ソだか分からん様な物であり正直言って美味い物ではなかったのである。果してこんな
物を口の奢った朝廷や高官、貴族たちが喜んで食べたのであろうか...。
「生蘇」の存在を認識するまで、長い道のりをたどった。修行と思えば足りない
ぐらいの回り道であったが、すでに何百キロという牛乳を謎の物体へと変えていた。
そして「蘇の四」までのような経緯があり「精蘇」から「生蘇」への再現と移行して行
ったのである。
朝廷はもちろん売れっ子作家の紫式部、古代セレブたちの舌を魅了させたであろう
「生蘇」の実態とは何か、腕の良い煎り人を雇い入れ作らせた「蘇」とは如何なる物
であったのか。残念ながらその製造法は、詳細には記されてはいない。が賢明な煎り人
であればその姿は見えてくるはずである。
「蘇庵の蘇」とは新鮮な生乳を使い、焦がすことなく姿は乳白色にて、
滑らかで香りよく、甘み、塩みは強すぎず、濃厚なれど繊細で、
淡味にして滋味である。
使う乳の特性を生かし、固すぎず柔らかすぎず噛みほどける
煎り合いが絶妙であれば至極の蘇と呼ぶに値する物なり...。

先頭へ

 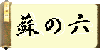 
 原乳 原乳
乳等省令(延喜式のようなものかな ? )上での生乳とは、搾取したままの牛の乳をい
う。牛乳とは、直接飲用に共する目的で販売する牛の乳をいう。
蘇を作るにおいて唯一の材料である原乳なのでもう少し詳しくその違いを説明する事
にしよう。
牛から搾ったばかりの乳を生乳という。(蘇庵ではこの生乳を原料とし製造する。)
この生乳を直ちに保冷却装置へと移し5゜C以下に冷蔵され数時間後タンクローリー車に
より何軒かの酪農家を回り収乳(合乳)され、大手乳業メーカーなどに運ばれ牛乳になる
為の儀式?が行なわれる。
受け入れ検査の後、清浄化され、標準化という工程に進むがここでは、ある一定の基
準に乳成分を調整する。要するに各酪農家で生産された個性ある生乳を同一にして製品
規格に合わせる作業である。
次に均質化であるが脂肪浮上によるクリームラインの形成を防止するため、脂肪球を細
かく砕き均等な状態にする。聞いた事があると思うがホモゲナイズド(均質化)と呼び、
市販の牛乳の殆どはホモ牛乳である。この工程では均質効果をよくする為に
60゜〜80゜Cの予備加熱を行なう。
そして殺菌であるが、以下の方法により区分されている。
低温保持殺菌牛乳 62゜C〜65゜C 30分保持殺菌
高温短時間殺菌牛乳 72゜C〜75゜C 15秒保持殺菌
超高温殺菌牛乳 120゜C〜140゜C 0.5〜4秒殺菌(スーパーなどで売られている牛乳は
殆どこのタイプである。)
(無殺菌牛乳 「特別牛乳」と言う物であるがこれはまた後で説明することにしよう。)
このような工程を経て瓶や紙ハ゜ックに詰められ10゜C以下に冷蔵され出荷される。
市販の牛乳の殆どは低温にしろ高温にしろ加熱殺菌がされている。
牛乳嫌いの人のほとんどは「あの牛乳臭いのが嫌、口の中がベタ付くのが気持ち悪い」
などと言うが、これは加熱の影響でタンパク質や脂肪が化学変化し臭いや粘性が強くな
ったと考えられる。出来れば搾ったばかりの生乳をそのまま飲んで頂ければ、
「えっ、本当に牛乳? 」って思えるほど違いが分かるんだが中々そうもいかないので、
驚いてみたい方は特別牛乳(無殺菌牛乳)を飲んでみる事をお奨めする。加熱殺菌されて
いないこの乳は、殆ど香りもなく後口は爽やかでベタ付く事はない。(本当ならこの無
殺菌牛乳も冷蔵しないうちに飲めれば一番好いんですけどね。)
牛乳とは、生乳100%ではあるが、過保護なくらい手を加えられている。これは私の持
論であり見解だが、近年では搾乳方法や衛生面、保冷機器等格段の技術進歩があり、生
産者も細心の注意を払い生乳(原乳)を取り扱っている。何時までも不味くする為にわざ
わざ高温殺菌を する必要があるのか疑問であるし、安全を盾に何事にもコスト面を優
先し本物を蔑ろにするのはいかがなものかと思うのだが...。
次回、加熱によって乳がどのように変化するのか、蘇製造にどんな影響を及ぼすのかを
実体験を基にお話したいと思います。

先頭へ

 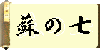 
 加熱の影響(ラムスデン現象) 加熱の影響(ラムスデン現象)
食品にしても殆どの物質は加熱に伴う何らかの影響を受け変化して行く。加熱処理が
乳に及ぼす影響には可逆的なものと不可逆的なものがあり、比較的低い温度での加熱処
理であれば不可逆的な影響を及ぼす事はないが蘇を作る場合低温であっても長時間の加
熱を強いられる事となるので様々な好ましからざる反応が発生する。
特に、以下のような現象が顕著に現れるので少し詳しく解説してみたいと思います。
皮膜形成(ラムスデン現象)、褐色化(メイラード反応)、たんぱく質の変性、加熱臭、
乳糖の結晶化などである。
今回は皮膜形成(ラムスデン現象)についてです。
牛乳を温めると表面に膜が張ってきます。(ラムスデン現象といいます。)大抵の方が経
験していると思いますが、これは乳と空気との界面に主としてラクトグロブリンからな
るたんぱく質の不可逆的な凝固が生成する為であり、初めの膜は脂肪を多く含み次第に
たんぱく質や乳糖も増加し、脂肪が7割ほどで残りの殆どはたんぱく質となります。
この皮膜が形成されるのは加熱して40゜C以上からであるが、この時点から湯気が立ち
上り臭気が漂い始めてくる。
(湯葉はこれと同じ現象から生まれた物、豆乳を加熱して出来た膜を箸ですくって生醤
油で食べる引きあげ湯葉はもー最高である。大豆の甘さと醤油のしょっぱさが口の中に
残っているうちに酒で洗い流すともう止まらない、だが焦ってははいけません次の膜が
十分に張るまでもう一杯飲んで待ちましょうね。ちなみに大豆は国産の物に限りますフ
クユタカというたんぱく質の多い品種が良いですよ)
さて、この美味しい皮膜であるが、蘇製造にはやっかいな現象なのである。
低中温により出来るだけ早く水分を蒸発させ濃縮させたいのだが皮膜でフタをされるこ
とになるので、休みなく掻き混ぜて行かなくてはならない。一度張った膜はダマになり
やすくコゲの原因ともなってくる。また鍋の縁に付着しやすくなり、気が付くと厚い層
となって固まり、蘇の仕上り時点で混ざり込む場合があるので注意が必要なのである。
以上美味しく、やっかいな加熱による影響、 皮膜形成(ラムスデン現象)でした。

先頭へ

 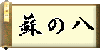 
 加熱の影響(加熱臭) 加熱の影響(加熱臭)
生乳を加熱し80゜Cぐらいから加熱臭(cooked flavor)が発生します。要はたんぱく質
の加熱変性であるが、これはβ−ラクトグロブリンからスルフヒドリル其(SH其)が遊離
することと関係があり、SH其が分解して生成する硫化水素(H2S)が加熱臭の主因である
らしい。
とあるアメリカ人が、日本のスーパーで売っている牛乳を飲んで 「オーマイガッ!
とても臭いです」と叫んだそうだ。
欧米では毎日飲む牛乳はパスチャライズド牛乳(パス乳)であり、超高温殺菌牛乳やロ
ングライフ牛乳は料理用か、保存用に使用しているらしい。日本では子供の頃から当た
り前の様に飲まされて来たので「臭いです」と言われてもピンと来ないかも知れない
が、逆にこの焦げをコクがあると感じている方も多いようだ。(牛乳に限らず菓子やフ
ァストフードにしても子供の頃から馴染のある商品の味には絶対味覚として鍛え植え付
けられているので何が本物であるのかが自身で判断出来なくなっているのではないだろ
うか...。)
蘇製造にこのヤケドした牛乳を使用し、加熱濃縮して行くとさらに加熱臭が強まる。
(長時間この臭いを嗅いでいると大変気分が悪くなる)完成した蘇は牛乳臭くパサ付いて
いて味も素っ気も無い。
蘇庵では厳選した新鮮な生乳を使用するので不快な臭いはしないが、加熱して皮膜形
成(ラムスデン現象)が生じる頃から、湯気とともに仕入れ先の酪農家(牧場)さんの匂い
が漂ってくる。私はこれを「牧場臭」と呼んでいるが、環境衛生的に優れた飼育管理の
しっかりした牧場の乳は、出来の良い乾草の香りがする。逆に不衛生で、飼育管理の悪
い所は大概飼料も粗悪な物を与えているので、乳自体飲んでも不味いが臭いもひどい
ものである。
「生乳を温めればお里が知れる」という訳である。

先頭へ

 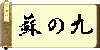 
 加熱の影響(メイラード反応) 加熱の影響(メイラード反応)
メイラード反応とはアミノカルボニル反応の一種である。
乳を100゜C以上に加熱すると褐色化(アミノカルボニル反応)する。これはカゼインのア
ミノ其と乳糖のカルボルニ其との間に反応が起こり褐色物質が生成されたものである。
異なる現象であるが、褐色化の一因となるキャラメル化は糖が引き起こす酸化反応であ
る。乳糖を100゜C以上長時間加熱すると酸が生成されるのでこれはキャラメル化と言え
るだろう。メイラード反応により独特の香気成分が生ずるが必ずしも万人向けとはいえ
ず、やはり牛乳臭いと感じる方が多数と思われる。
蘇庵の蘇は生乳の自然な風味をなるべく壊したくないので高温での濃縮は行なわず、
メイラード反応のような褐色化や香気成分をあえて生じないようにしています。
一時生キャラメルが流行り、テレビなどでその作り方をよく紹介されていましたね。
無垢のきれいな銅鍋に牛乳を注ぎいれ掻き混ぜていましたが、キャラメル化すれば褐色
反応が生じ緑青などが溶け込んでも気にするほどではないのだろうけど...。
昔は緑青は有害といわれてましたが現在は無害が定説となっています。銅イオンは殺菌
効果を生み出し、餡子やジャムなどはその色合いを好くする為に古くから使われてきま
した。
蘇庵でも銅鍋を使っていますが長時間の加熱濃縮でも乳白色が損なわれないように内
側に錫メッキがされたものを使用しています。熱伝導性が良く蒸発率が高いので蘇作り
に適した鍋といえるでしょう。
また気候が好くなり眠くなった時など、木杓子で鍋の縁を叩きます。「コォーン」と澄
んだ音色は身体の心までに響き、精神を集中させてくれる効果もあります。

先頭へ

 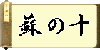 
 加熱の影響(乳たんぱく質の変化) 加熱の影響(乳たんぱく質の変化)
牛乳のたんぱく質は主にカゼインとホエーたんぱく質により成る。カゼインの熱安定
性が高いのに対してホエーたんぱく質は熱変性(加熱臭など)や凝固を起こしやすく不安
定である。
カゼインは100゜C以下ではほとんど変化しないが、酸や塩、擬乳酵素、アルコールお
よび熱の作用によって凝固する。乳の酸度が高くなるとカゼインがアルコールにより凝
固する。この性質を利用して原乳受け入れ検査では先ずはアルコールテストを行なう。
また擬乳酵素(レンニン)による牛乳の凝固はカゼインの変化によるものでチーズ製造の
原理となっている。
牛乳たんぱく質からカゼインを除いたものをホエーたんぱく質(乳清たんぱく質)と云
い。熱によって凝固するので熱凝固性(熱不安定性)たんぱく質ともいわれている。
蘇を短時間で作るには高温で加熱して行けば水分の蒸発も早いのであるが、たんぱ
く質の変性凝固の方が優先されてしまいメイラード反応の進行によりすぐに焦げてしま
うのである。乳たんぱく質は長時間の加熱濃縮に伴い粘度の上昇をきたしやがてゲル化
に至り蘇へと変貌して行くのであるが、蘇を乳白色に仕上げるには適切な加熱温度が要
求される。何より時間と気力を費やさなくてはならない訳である。短時間での濃縮を望
むなら減圧式のコンデンサーなど機械処理で製造すればあっという間であろうが、それ
では蘇としての価値観もロマンも見出せないのである。収益性は望めないがやはり鍋ひ
とつでじっくりと作りたい。まったく商売っ気のない蘇庵である...。

先頭へ

|